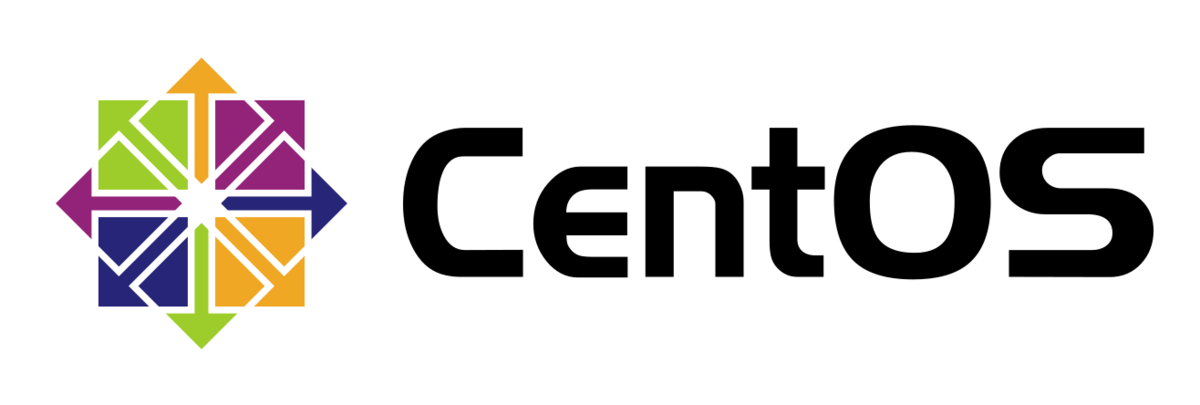ポストMOOCの時代に取り残される日本
前号でご紹介した通り、オンライン教育を活用したオープンエデュケーションの活動の一つであるMOOC (Massive Open Online Courses)は、2012年頃には、ニューヨークタイムズから、``The Year of the MOOC''と讃えられるほどの目覚ましい発展を遂げていた。一つの講座に100万人単位の学習者を集めることに成功し、大学のあり方を劇的に変えてしまうのではないかと米国で騒がれたのだが、その事情は、最近に至るまで日本ではあまり知られることは無く、周回遅れのように、米国でのブームから1年ほどして、日本でも漸く話題になった。
しかし、日本で騒がれ始めた2013年後半からは、米国では、オープンエデュケーションの活動はポストMOOCの時代に入ったといわれ、MOOCについての様々な反省が取りざたされるようになっている。
2014年に入ってからは、米国でのMOOCの話題は急速に下火になってきており、MOOCという言葉はもはや死語になるだろう、とまで言われはじめている。この時期に来て、日本では2014年4月からJMOOC(社団法人日本オープンオンライン教育推進協議会)の活動が始まり新聞報道も盛んに行われるようになったところである。
JMOOCそのものは、日本におけるオープンエデュケーションの立ち遅れに対する強い危機感から創設された法人であり、その活動がなければ、オープンエデュケーションにおける日米格差の事情はもっと大きくなっていたはずであるが、それでも、相変わらず米国の周回遅れになっている状況は十分には改善されていない。
日本の事情は後に触れることとして、米国におけるMOOCの反省点はいくつかある。とくにMOOCのなかで最も華々しい成功を収めたMOOCプロバイダーであるCourseraは、巨額の資金を集めに成功したが、その分、余りにもお金をかけすぎていると批判を受けている。加えて、学生の学習完遂率が数パーセントにとどまる点や当初の目的とされていた企業マッチングにも成功していないなどの失敗も指摘されている。
MOOCは大学では無いので、その履修証明のブランド価値は、企業に評価されて初めて意味が出る。このため、企業マッチングがうまく機能しないようであれば、MOOCの行方に不安があるとの指摘は当たっているだろう。こうした事情からか、最近ではダフニー・コラーと並んでCourseraの創設者であったの二人のうちの一人であるアンドリュー・ングがCourseraを事実上去るのではないかと報道された。
2012年のMOOCが華やかに喧伝された当時、MOOC三大プロバイダーと言われたCoursera、Udacity、edXのうち、残る2つのプロバイダの情況も大きく変化している。
セバスチャン・スラン率いるUdacityは、2013年終わりには、大学との連携に見切りをつけ、企業と直接タイアップしたプロフェッショナル向けのエデュケーションを展開しようとしている。また、MIT、ハーバードなどが出資するedXは、各大学の事情に合わせたオンラインコース、SPOC(Small Private OnlineCourses)を展開しようとしている。
それぞれのプロバイダが、それぞれ当初の道とは少し異なる道に活路を見いだそうとしている。これがポストMOOCの時代の第一の面である。
しかし、より重要な点は、ポストMOOCにおいては、その強い影響を受けた多くの大学が、新たなオンライン教育の活路を見いだそうとしている。ここにポストMOOCのもう一つの面がある。
MOOCが一時のブームだったとしても、高等教育機関におけるオープンエデュケーションのブームが終わるわけではない。これからの時代は、オープンエデュケーションは様々姿を変えてやってくる時代になったのである。
南ニューハンプシャー大学の奇跡
米国北東部の小さな大学だった南ニューハンプシャー大学は、2009年までは、学>生数わずか2,000名、財政的にも苦しい経営を迫られ明日にも倒産と思われていた大学だった。
しかし、その時学長に就任したルブラン博士は、オンラインとコンピテンシーベースの教育(教育すべき内容を細かい単位に分割し、個々の学習者に合わせたセミオーダーメード型の教育を行う事)を梃子に、わずか数年で大学のありようを一変させ、今日では学生数3万5千人を抱える大学にまで成長し全米を驚かせ、新たなオンライン教育の可能性を示し、ポストMOOCに大きな影響を与えた。
南ニューハンプシャー大学のコンピテンシー教育による工夫は、大学のアマゾンと呼ばれている品揃えの豊富さにある。実際Webページを覗いて見ればわかるが、そこには学習者が望むと考えられる多様なコースが置かれており、学位や資格取得などに必要なコースを組み合わせて履修するための情報も必要かつ十分なまでに充実している。発行される学位は多様であり、大学院の学位もある。
何よりも大学のWebページにある ``Best Buy'' という安売りショップのようなセールスコピーがなによりもそのあり方を示している。
この大学のさらなる魅力は、オンラインを含む他のどのような大学と比較しても、低価格でしかも短期間に学位取得が可能なことにある。高い学費に苦しむ米国の学位取得希望者に一躍人気になったのも道理である。
マネージメントも工夫が凝らされている。南ニューハンプシャー大学のオンラインコースの教員たちは、研究業績を求められない、代わりにコース当たりのインセンティブがあり、数多くのコースをこなすことにより、それなりの水準の収入が確保できる。
その活動はMOOCがブームとなる以前からのものであるが、オンライン教育がすべてを変えてしまうというレバレッジの大きさを象徴してい
るという点でポストMOOCの大きな柱である。
最近では、アイルランドの大学が連合してオンライン教育を始めようとしているが、そのベンチマークには、MOOCと南ニューハンプシャー大学がある。
グローバル化とオープン化
オックスフォード大学社会学部教授の苅谷剛彦氏は「『国際競争力』の幻想に惑わされた日本の大学改革」(2014年2月)の中で、日本の教育のグローバル化について言及し、そもそも非英語圏である日本は、グローバル化と言ってもリアルな競争はできず、「想像上」の競争に過ぎないと指摘している。日本語という壁がオープンであるべき情報を阻み、本当の意味でのグローバルな競争を阻んでいるという指摘である。
高等教育機関を英語ではなく母語で受けることができるという国は、そう多くは無い。日本の高等教育はその点で独自の文化で有り、誇るべき点でもあるかもしれない。国際的に活躍してきた多くの大学人がその点を指摘する。しかし、そのことが同時に世界の中での孤立を生むという問題もあることをこの論説は示唆している。
反面、グローバル化は、米国のご都合主義と考えることもできる。米国文化の無理矢理な押しつけがグローバリゼーションである、という論説を時々見かける。
しかしそうした論説にも見落とされているものがある。グローバリゼーションの波には、実はオープン化という米国固有の文化が付随しているという点である。
反知性主義とオープンな文化
米国では1950年代のマッカーシズムに典型的に見られたような反知性主義(anti-intelectualism)が優勢であり、高等教育を無用の長物とみる風潮がある。
反知性主義の起源は、実は、コンピュータなどは全く無縁の米国開拓時代を遙かに遡るとされている米国の伝統でもある。エリート大学はこの対応に苦慮してきたが、冷戦の最中に学術研究の役割が見直されて以降は今日に至るまであまり表だつことはない。しかし、知性(intelectual)よりも知識(intelligent)が重視され、実践的な成果が求められるという風土が変わったわけでは無い。
米国の高等教育機関がオープンにこだわるのは、反知性主義に対する配慮という側面があるだろう。施設を地域に開放し、成果を社会に還元するといったオープンな活動を積極的に展開することは、マッカーシズムによる「反知性主義」を経て、冷戦時代に多額の軍事にかかわる国費を費やして成長してきた米国のエリート大学にとってのカードの裏表のような関係がある。
インターネットもまた、そうした米国エリート大学の一角で軍事経費によりスタートアップできたことを考えれば、その性格は一層明らかになるだろう。
そしてインターネットの登場とともに、米国固有の反知性主義の高等教育機関の反動だったはずの、オープンな文化は大きな変貌を遂げることになる。
オープン化は、まず第一の波としてLinuxなどのオープンソースがあり、これはやがて教育研究分野を出て、Googleなどの成功に象徴されるように、インターネット上のビジネスもオープンに基づいていることと切り離せない関係にまで根付いた。
反知性主義的な米国が、オープンという知性的な文化を生み、米国発のグローバリゼーションを支えるという倒錯した関係がここにできあがった。
オープンの波は、現在もさらに新しい波を生んでいる。第二の波としては学術雑誌のオープンアクセスがあり、この動向は、単に学術雑誌に留まらず、出版業界に大きな変動を引き起こそうとしている。
オープンエデュケーションは、これに続くオープン化の第三の波なのであり、ほかの2つの波と同様にやがて教育研究分野を越えて広がって行くだろう。
実際Udacityの取り組むプロフェッショナルラーニングがその一つの答えの一端になっている。
オープンな文化と自前主義文化
日本では、グローバル化が叫ばれても、それと裏腹な関係にあるはずのオープンな文化については殆ど意識することがない。ここには、日本では、オープンという文化を受け入れがたい強い事情があることを示唆している。
私はこの事情を日本文化の「自前主義」と呼んでいる。高度成長期を経て「日本的経営」とバブルの頃持て囃された日本の企業体質もその内実は「自前主義」だったのであり、日本でもっとも成功している企業であるトヨタは、自前主義をもっとも典型的に体現している企業だとも言える。
自前主義のオープンな文化への態度は、オープンソースの日本での扱いにみ
ることができる。
日本ではオープンソースの活用は盛んに行われている。企業は、オープンソースを活用し様々なサービスを提供し、製品を作り上げる。しかし、オープンソースの提供者であるコミュニティには、何の還元もしない。当然のごとくに無料で利用するだけで終わりである。
米国では、IBMをはじめとする大企業がオープンソースに対して巨額の
支援をしているという事情とは正反対である。
米国で多くの優れたオープンソースが生まれ、日本では僅かの例外を除いて、殆どオープンソースへの貢献が無い理由である。
さらに面白いことに、米国にあってもIT系の日系企業は、米国のコミュ
ニティにはかなりの支援を行っている。日本では、オープンソースコミュニティには全く見向きもしない企業がである。
オープンへの取り組みが、文化的な事情に根ざしているということを象徴している。
日本の高等教育においてもその事情は同じであり、オープンであるよりも前に「自前主義」を貫き、一つの大学の中の閉じた環境の中で教育を提供しようとする。
日本の私立大学が800にも及ぶのはいくつかの理由があるにしても、「個
性的な」教育を「自前」で提供するという文化がそれを支えているという一面がある。本当にオープンな環境の中で800もの「個性的」な組織が生き残ることは難しいであろう。
苅谷氏の言うとおりグローバル化は英語圏でもない日本では茶番であるが、その内実のオープン化は、本来英語圏であるかどうかに関わりの無い事態であるにもかかわらず、無関心もしくはあまりに無知である。
グローバル化だけが叫ばれても、肝心のオープンな文化という中身を捨ててしまっている以上、グローバル化が日本で普及しないのも道理である。
安楽死する日本の大学
日本の独自の「自前主義」文化の中で日本の大学は静かに息づいている。
いまはそれでも良いかもしれない。日本の大学の市場は日本の学生であり、世界の動向とは今の所は無縁である。
一方、これを世界全体から見たときに何を意味するのだろうか。このまま独自の文化の中で繁栄を続けることができればそれはすばらしいことでもある。しかし日本の外では、すべてが英語で行われている研究成果や効果的な教育手法の「オープン」な成果物を日本のそれぞれの大学が「自前主義」で日本語化し、JMOOCの例に見られるように、そこからゆっくりとしかも独自に普及させて行くという手法だけしかなければ、日本はますます孤立化し、教育を基盤とするすべての世界的な競争に取り残されるということになる。
若者が、オンラインを通じて世界の大学に容易に入学でき、企業は日本
の大学よりもオンライン教育で育った若者に価値があると気が付いたときに、日本の大学は教育という面で価値もないものになるだろう。
大学の関係者のだれもが「ぼんやりとした不安」を抱いている。同時にそんなことはありえないとも思っている。文部科学省を含め、大学に関わる度合いが強い人ほど、大学がオープンオンラインごときに影響を受けるはずは無いと思っている。
大学業界の中心から少し離れた周囲にいる人たちの中には、強く懸念する人たちがいることも興味深い。しかし、その声が大学関係者に届くことはほとんどない。
現在の大学は、少子化という目の前の危機があり、ほとんど競争というものを知らない大学業界は、企業的には多くの問題を抱えている。その限りでは、オープン化などに構っている余裕は無い。ところが他方では、大学の倒産はここ10年あれだけ騒がれながら、数えるほどしかない。そんな中では、海外の動向にまで目配りして、大学に対する危機感を持つという動機が乏しくともいたしかたの無いところである。私はこれを日本の大学の「安楽死」とよんでいる。
日本が安楽死する日
「安楽死」は、日本の大学だけではすまないかもしれない。文化的な敗北は、大学と同じように「自前主義」の日本の企業の安楽死を引き起こし、遂には、日本全体の安楽死につながるかもしれない。
オープン対「自前主義」は、日米の固有の文化の衝突であり、オープン化への従属は、日本の固有の文化の破壊である、という見方もできる。
皮肉なことに、「自前主義」の中に甘んじ、オープンな文化に慣れていない日本においては、クローズにすることも不慣れである。日本の多くの製造技術は中韓に流出したが、同じ中韓は米国ではそのような恩恵を被ることはないし、iPhoneで成功するApple社は、これだけオープンな環境の中で次期製品情報を流出させることは決して無い。日本の「自前主義」文化が甘えを生み、世界的に見れば脇を甘くしているとも言える。
その点だけを考えてもオープン化は、強力な武器であることがわかる。オープンであることにより、多くの人々に知識を提供し、コミュニティを形成し、一個の力では到底到達できないプロダクトを作り出す。その典型的な結果が、先にも述べた、オープンソースにおけるLinuxであり、Googleがオープンな戦略により一人勝ちを納めたケースである。
日本的「自前主義」対オープンの戦いは、1対1での戦闘しかできない日本の古武士が、集団戦闘の海外の軍団と戦うようなものである。個々の能力の高さだけでは、チームワークに勝利することはできない。勝負は闘う前から着いている。
魯迅の小説「吶喊」の自序では、当時の中国の安楽死を拒否する魯迅の強いメッセージが載せられていた。一国の安楽死の危機を前にして、日本では、いたずらに愛国心を煽る輩はいても、当時の中国における魯迅のような自覚も意識も持つ人はいない。オープンな文化に対する意識は「知性」を代表するはずの大学でこそ自覚されなければならないはずである。しかし日本においては、肝心のその大学が、「自前主義」に徹して、経営者は今年の入学者数に気をもみ、教員は過重な業務負担に追われ、大学人は、誰もが目の前の問題にしか目が行かないという体制の中にある以上、安楽死への警鐘を鳴らすものがだれもいないという事態
も仕方の無いことである。
私自身は、「愛国心はならず者の最後のより所である」というサミュエル・ジョンソンの言葉を愛するので、愛国心に燃えて安楽死に憤るということは好まない。日本が安楽死することも悪くは無いと思う。
しかし、オープン化により多くのチャンスを手に入れることができるのに、「自前主義」にこだわり続けて、チャンスを失うのはちょっともったいないという気はしている。
(櫻井ゼミ同窓会誌『対話』第3号 2014年6月21日発行 所収)